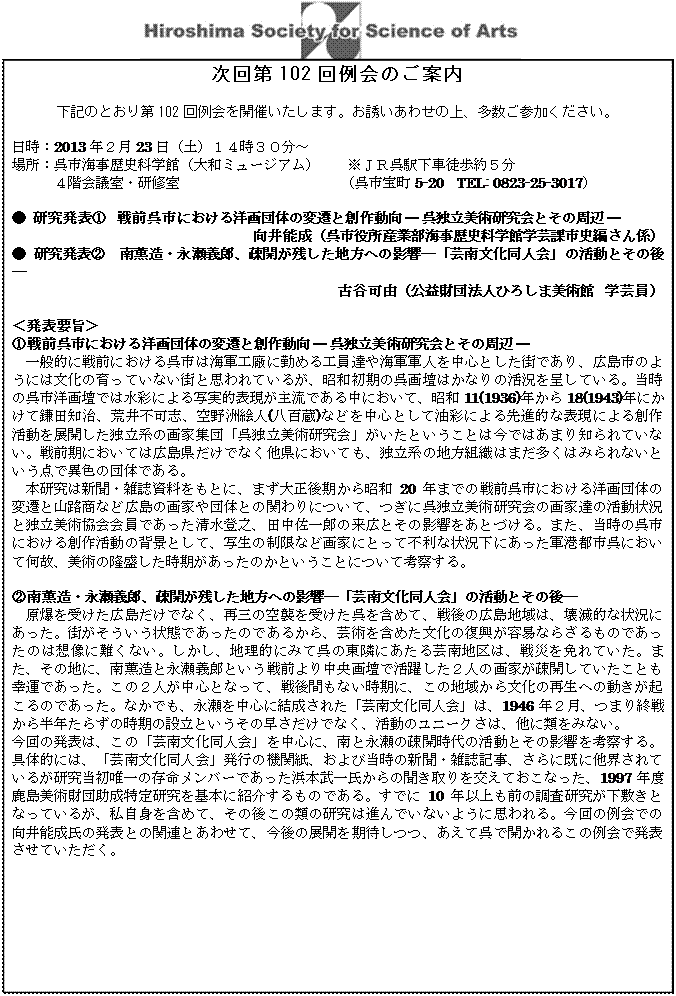広島芸術学会会報 第121号
● 巻頭言
月の光の宿のほろび
大井健地(広島市立大学名誉教授・美術評論)
「お父さん、今まで旅行のうちで、いちばん悪かった宿屋はどこ」。
と、問われた柳田国男(1875?1962)が「別に悪いというわけではないが」「小さくて黒かった」宿として挙げるのが、現岩手県九戸郡洋野町小子内にあった清光館。
宿泊日は1920年の旧暦7月14日、お盆の日。その描写。
「清光館と称しながら、西の丘に面してわずかに四枚の障子を立てた二階に上がり込むと、はたして古くかつ黒い家だったが、若い亭主と母と女房の親切は、予想以上であった」。
文中の「若い亭主」とは30代の菅原喜三郎。先代連次郎(1860?1919)の弟哲郎の子。2年後の1922年の暮れ、回漕船の海難事故で死亡。「母」とは義母ハツ。連次郎の妻。1901年5月頃開業の清光館は喜三郎没年の翌1923年秋閉業となるがハツが実質の営業人でありおかみであった。
集落の人は誰も清光館とは呼ばない。「菅原の家」であった。清光とは月の光のこと。
なにャとやーれ
なにャとなされのう
女だけの踊り。何なりともせよかし、どうなりともなさるがよい。「歌は、恋の世界への自由な解放、快楽への耽溺を求める叫びであった」。「この海辺の女人たちの盆踊りの歌のデカダンスの意味を」(益田勝実)感じとれるかどうか。
「清光館哀史」(1926年、全集2巻収録)は筑摩書房高校国語の定番教材だった。あァ何でもせいという虚無的起爆力を生徒はきっと理解できる。何にも心配ない。「あさはかな歓喜ばかりでも」ない。「やるせない生存の痛苦、どんなに働いてもなお迫ってくる災厄、いかに愛してもたちまち催す別離」(柳田国男)、それらを想像できる若い人々の感受性を信頼する。
近年の柳田論では遠藤誠治の「哀史」論が新鮮。これはユゴー『レ・ミゼラブル』が『哀史』と長く訳されていた事実、また細井和喜蔵『女工哀史』刊行は柳田の小子内再訪と同年の1925年であることに注目する。柳田民俗学は経世済民の思想に直結しているのだ。民衆を救え。悲惨な「常民」の現実を見よ。
国際連盟委任統治委員会の一員としてのジュネーブ滞在から帰国の翌年、「鮫の港に軍艦が入って来て混雑しているので」「なんということなしに陸中八木の終点駅まで」来た柳田。その後八戸線
参考文献:松本三喜夫『柳田国男の忘れもの』青弓社2008年。『名指導書で読む筑摩書房なつかしの高校
国語』ちくま学芸文庫2011年。
●
第101回例会報告
研究発表報告①
歌川広重の特徴ある風景表現について―複数の透視図が共存する重層的透視図法―
発表:中曽政行(広島大学大学院教育学研究科博士前期修了)
報告:谷藤史彦(ふくやま美術館 学芸課長)
歌川広重の構図法には独自なものがあり、欧米への影響も決して小さいものではなかった。イタリアではG.ファットーリやT. シニョリーニの作品にその影響が見られ、またアメリカではF.L.ライトがその建築パースのなかで広重へのオマージュを捧げているほどである。
中曽氏は定年退職後に大学院に進み日本美術を研究してきた異色の研究者であるが、広重の透視図法に惹かれる中で、先行研究だけでは説明できない作品に突き当たり、独自の解釈に基づく研究を進めているという。具体的には、「江戸名所百景 京橋竹がし」の画像を、「重層的透視図法」と称する方法で分析してみせる。それは、遠景に描かれる竹と橋脚の高さと、近景の竹と橋脚の高さとをそれぞれ比較する手法で、近景の竹が極端に大きく描かれていることを明らかにする。また、同シリーズの「鎧の渡し小網町」における蔵の描き方、「高田の馬場」における並木などにおいても、例解してみせる。それは、広重がこだわったモチーフを誇張し、実景のように見える風景のなかにもぐり込ませる手法であった。「虚構を虚構として感じさせない風景画を描く「写生の絵師」としての広重の自負がさせた試みのひとつだった」と結論づけた。
中曽氏の提案は、先行の「近像型構図」法では説明できない作品に対する試論として考案されたものであり、その他の作品の説明にも有効な構図解析法だという。しかし広重自身がそれを意識的に試していたかどうかの確証は示されなかった。そこで中曽氏の提案に説得力をもたせていくためには、次のようなことが必要かと思われる。つまり、大久保純一氏が『広重と浮世絵風景画』で言及する「消失圏」という考え方と、「重層的透視図法」との違いについて、および当時の史料などを使っての裏付けの研究などが進められることである。今後の研究を期待したい。
研究発表報告②
室町時代の山水図屏風にみる文人イメージ
発表 城市真理子(広島市立大学 国際学部准教授)
報告 青木孝夫(広島大学大学院 総合科学研究科教授)
室町文化の中、例えば絵画に関し何を思い浮かべるだろうか。日本的な土佐絵も興隆したが、中国文化を受容して生まれた水墨画の存在が大きい。しかし、山水画は大方の聴衆にとって地味な上に、加えて鑑賞には漢詩の解読が必要というのだから、敷居は高い。
しかし、城市氏は、この絵画と漢詩の響き合いの意味を読み解くことで、五山に集った禅僧や文化人の間で、如何に水墨画が楽しまれ、また創作されていたかを、まずは教えてくれた。
室町期水墨画を代表する一人、周文の現物は殆ど残らないが、この源泉から流れ出た岳翁蔵丘・雪舟など周文派の代表的作品を通し、解明は進められた。水墨画を単に美術として、絵画の技法や様式の元を辿り、あるいはその受容や変化の流れの中で画面を捉えるだけでは不足である。上に述べたように、画面と画賛の響き合いの解読を通して、水墨画の味読は進められる。伝周文の「竹斎読書図」は縦長の詩画軸で、比較的小さな作品である。(この作品は、e国宝 http://www.emuseum.jp/ で子細に検討できる。) 画面上部には序があり、その下に五人の禅僧が漢詩を寄せる。その画賛の検討を通し、画中世界への言及だけでなく、制作状況や交遊関係も察知される。鍵は中国の伝統的な文人文化への憧れである。城市氏の言葉で「文人趣味」である。日本の禅僧は、その身分立場等々からして、普通の文人ではないが、しかし教養・生き方として文人である。
水墨画には、文人憧憬の風景や境地やまた人物・場面が描かれて、これを見る者の憧れ、教養を鳴り響かせる。そうした観点からみると、比較的小品の詩画軸も屏風図のような大画面でも、同じことである。この場合、画賛ではなく、主に画面の解読を通して検討が進んだ。
例えば、伝周文筆「四季山水図屏風」(真宗大谷派名古屋別院)には、瀟湘八景を四季の山水図屏風にアレンジしたものと解釈できる面がある。右隻と左隻に対応対照的に見られる晴と雨の風景描写には、瀟湘八景の画題だけでなく、中国文人共通の詩題でもある「晴好雨奇」の教養が鳴り響く。この主題は、西湖に縁の文人達、白楽天や林逋の中でも、特に蘇軾である。彼に関しては、また画中の楼閣に描かれた三人の人物と関わる。この三人が、三蘇として比定される時、画面の前で、蘇軾の親子兄弟の仲良さ等について好んで語る五山の文化人の交遊の姿が彷彿とする。更には、臥游よろしく、画面の中に入り込み、三人と対話せんとする日本の禅僧の中国文化憧憬の度合いも察知されよう。知識は、画中の楼閣の三人の人物の比定や絵解きに利用されるだけでなく、いわば、見る人も画面の中に入り、彼ら理想的文人と一緒に会話を楽しむのに役立つ。本場から離れた日本で、絵画と漢詩の制作と享受を巡り、時空を或いは同じくし或いは隔てた文人同士の教養と友情の競演が演じられる雰囲気が五山の世界にはあった。
このようにして城市氏は、室町水墨画を当時の中国憧憬の文化環境の中に置くことで、画面や画賛の主題や細部の有つ生き生きとした意味を照射し蘇らせ、我々に馴染みの薄い世界と思えたところに、広島の縮景園や厳島八景と地続きの、また頼山陽や菅茶山の親しんだ世界が広がっていることを示してくれたのである。
● 加藤宇章氏、県民文化奨励賞受賞
この度県民文化奨励賞を受賞された当会会員の加藤宇章氏に、一文を寄せていただきました。
県民文化奨励賞を受賞して
加藤宇章(造形作家/アトリエぱお造形教育研究所代表)
昨年末、私は「けんしん育英文化振興財団」から「県民文化奨励賞」を贈られました。受賞理由は「造形芸術の制作と造形教育の普及」への評価と「今後の創作活動と文化芸術の振興」への期待とのことです。日頃の活動に対しての受賞に「どこかで誰かが見てくれている」ことを喜び、「私もようやく広島人に成れた…」と感慨深いものがありました。
東京藝大卒業後、恩師の元で10年間続けた造形教育のより自由な実践を望み、長崎出身者のシンパシーだけで広島を造形教室「アトリエぱお」開講の地に選んだのが、約19年前のこと。周囲には「地縁血縁のない街に良くぞ来た」と言われるのですが、妻の後押しと「直感」で自分としては迷いのない決断でした。
幸い、私と私の家族は広島との相性が良く、市民にも受け容れていただき、気がつけば広島は50余年の人生で最も長く暮らす街となりました。制作ではテラコッタを中心に発表し、様々な作家や市民とも繋がりができ、そこから広島市立大学をはじめとし造形教育の場もひろがり、こども造形や障がい者美術のコンクール・展覧会の企画運営など普及活動にも参画できました。また、それらの出会いから受けた刺激はアトリエぱお独自の造形教育や自分自身の制作にも活かされていると感じています。
広島に転居して以来の、全ての出来事、全ての出会いに深く感謝すると共に、受賞を励みにこれからもますます精進をしようと、身の引き締まる思いでおります。
1960宮崎生まれ 1962長崎に転居 1984東京藝術大学彫刻科卒業、浦和造形研究所こども造形講師就任 1994広島に転居し「アトリエぱお」を開講、代表を務め現在に至る 2003「広島の美術」奨励賞 2012八千代の丘美術館入館・クロアチア Zagreb FLag Art Competition 大賞 他 個展・グループ展多数 広島芸術学会会員 新制作広島グループ会員 広島市立大学芸術学部他、非常勤講師 アートルネッサンス展他、審査員 広島大学大学院教育学研究科在籍
加藤宇章(溝尻隆志) Kato Takafumi (Mizojiri Takashi)
アトリエぱお造形教育研究所 代表 (有限会社パオパパス)
● 展覧会レポート
必見!広島の奇才親子 ~「船田玉樹展」「船田奇岑展」を見て~
松波静香(ギャラリ―G)
この度、生誕100年を記念して、船田玉樹展が広島県立美術館で開催されている。それに併せて、息子である船田奇岑の個展も広島市内2カ所で同時開催された※。
船田玉樹の作品ですぐに思い浮かぶのは、『花の夕』や『紅梅(利休像)』だろう。これらは昨年同館で開催された特別展「日本画の前衛展」の中でもひと際強い印象を残した。それまで知る人ぞ知る存在だった玉樹だが、この「日本画の前衛展」で一般にも知られるようになったのではないだろうか。
船田玉樹(1912-1991)は呉市広出身の日本画家。古典を礎とし、画材や構図の研究に明け暮れ、日本画の未来を想い続けた。展示作品は、玉樹の画業を振り返る六曲一双などの大作群をはじめ総点数230点余り。師である速水御舟、小林古径、また影響を受けたと考えられている安田靫彦や岩橋英遠、山路商、盟友の丸木位里、靉光などの同時代作品も並んでいる。おもしろいほどに変わっていくその画風は、時に観る者を圧倒させ、また時にはくすっと笑ってしまうような人間臭い一面も見せる。型にとらわれない作品たちからは、玉樹の探究心や好奇心がひしひしと感じられた。
船田玉樹とはどんな人物だったのだろう。1月27日に開催された山下裕二氏と船田奇岑氏の対談「船田玉樹について語る」の中で、息子の奇岑氏が見ていた玉樹の日常の様子を聞く事ができた。資料として展示されている直筆の文章「わたしはかうして絵の道へ入った」や、療養中に作ったという詩にも、その魅力的な表情が垣間見える。また、今回も展示されている河童シリーズに登場する河童は、玉樹が自分自身を重ねているという。絵に添えられている詩からも、その人間性が想像できる。
末の息子である船田奇岑氏は、玉樹が体調を崩したことをきっかけに父の仕事を支えはじめた。亡くなった後も玉樹作品の管理、整理、修復、洗い、鑑定などを一手に背負っている。自身も日本画家として活動し、国内外で評価を得ている。今回の玉樹展に併せ、広島三越(八丁堀)とギャラリ―G(上八丁掘)で自身の個展を開催した。
三越では、牡丹や椿を描いた季節を感じる掛け軸や屏風などを展示販売した。奇岑氏らしい粋な軸装が印象的だった。会期中行われた奇岑氏のテルミンと榊記彌栄さんの箏の演奏では、画廊から人があふれるほどの盛況ぶりを見せた。
一方、ギャラリ―Gでは1994年以降の転機となった作品と実験的な近作を展示。 1階に展示されたのは、94年第3回公募「広島の美術」で佳作を受賞した「日の丸」と2001年に東京のアートフロントギャラリ―(当時のヒルサイドギャラリー)の個展で出品された屏風絵「夏の海に降る雪」と掛け軸の3点。 「パーツの描き方は父から学び、すでに習得していた。それをどう父の真似にならずに自分の作品として描けるか、30代?40代はそれを試行錯誤していた」と語る奇岑氏。確かに、「日の丸」の画面には枝や花が描かれているが、枝は幹から伸びているわけではない。花も枝についているわけではない。枝が集まって太陽のようなものを形作り、水の流れも空中から生まれているように見える。ばらばらにして再構築し、別ものになろうとしている。 「夏の海に降る雪」もいろいろなパーツが集まり、様々な見方ができるような画面になっている。この作業が40代後半には納得が行くところまで達し、そのころから玉樹展へ向けての準備をはじめたそうだ。約10年をかけて、父玉樹の作品の整理、洗い、軸装などを進め、ついに今回の展覧会開催を迎えたという。 ギャラリ―Gに在廊していると、生前の玉樹を知る方が続々と来られる。そしてしばらく思い出話や噂話をしてくれる。お会いしたことはないのに、そうでないような錯覚に陥る。亡くなった今もその存在は大きい。 この魅力的な広島が誇るべき奇才の作品を一堂に見る事ができるのは初めてとなる上、このような親子同時開催展はめったにない機会である。できれば何度も足を運んで目に焼き付けておきたいし、広島の方には見逃してほしくない。また、ギャラリ―Gの2階には奇岑氏が医学部で学んだ経験を生かした実験的な近作が展示されているが、玉樹展が終わってからの奇岑氏の制作活動も楽しみだ。 ※「生誕100年記念 船田玉樹展」(広島県立美術館 1月21日~2月20日) 「船田奇岑展」(広島三越 三越画廊 1月22日~28日) 「船田奇岑展works1994~2012
Death And The Flower」(ギャラリ―G 1月22日~2月10日) ● エッセイ お断り:昨年11月末に投稿された文章ですが、紙幅等の都合で今号に掲載しました。(会報部会) 秋の虫が鳴く頃… 袁 葉(広島大学) (一) 北京の実家のソファーに腰を掛け、好物の生のナツメをつまんでいた。ふと、手が止まった。「釣魚島、日本国有化…」というアナウンサーの声を耳にしたのである。今年9月11日のこと。 よかったー。里帰りして三週間、すでに会うべき人には会ったし、昨日の天津の親戚訪問が最後の「行事」だった。残り2日間はお土産を買ったりして、あとは広島に帰るだけだ。とにかくこの問題について、周りから質問されなくて済む! ・・・・・・ 自宅に着いて、まずパソコンのスイッチを入れた。広島フィルムコミッションからのメールを開けると… わおっ、『長江哀歌』のジャ・ジャンクー監督が広島にやってくる! 中国人映画監督を招いての、作品上映とトークショーの第2弾である。前回はまる一年前、『山の郵便配達』のフォ・ジェンチイ監督だった。イベント開始5分前に通訳を頼まれ、冷や汗をかいたのが記憶に新しい。 また、芸術の秋が巡ってきた。 (二) テレビ画面の中を、反日デモの大群衆がこっちに向かってやってくる。デモ隊が毛沢東の肖像を掲げているので、つい無産階級文化大革命時代の行進とダブって見えてしまう。当時は、「毛主席最新指示」が下される度に行われていた。 毛沢東の肖像が掲げられたことについて、日本の政治家や評論家は「現政権への不満を表わすものだ…」と解釈するが、的外れだと思う。 もし50歳以上の世代ならありうるが、参加者の大部分が30歳代以下の若者ではないか。79年から推進された「独生子女政策」により、彼らのほとんどは一人っ子だ。また、同年スタートした「改革開放政策」がもたらした、建国後未曾有の物質文明の発達の恩恵を享受してきた世代である。したがって、つぎ当ての服を身につけ、三食ありつくのがやっとの毛沢東時代へのノスタルジーなど、あるはずがない。 毛沢東は抗日戦争を勝利に導き、建国の父だという教育を受けているから、反日の象徴として肖像を掲げたものと思われる。 (三) 一枚の蟹の墨絵。そこに淡い点々が付け加えられると、さざ波の中にいるようにも、砂浜を這っているようにも見えてきた。それは、鑑賞する側の心象次第である。水墨画の「写意」と西洋画の「写実」を比較して、東西の美学について語っているのは蔵新明教授だ。日本で活躍する中国の画家であり、ルーブル美術館の展覧会にも出品したことがある。 前かがみで聞く人や手帳にペンを走らせる人、写真を撮る人などを眺めて、ああ、この企画をやってよかったと思った。9月28日の夜、私の属する女性異業種交流会の定例会でのひとコマだ。 ちょうど40年前の今夜は、「日中国交正常化」の前夜に当たる。しかし、40周年の祝賀行事が、日中間の「政凍経冷」のため、相次いで中止に追い込まれている。企画に携わった人、楽しみにしていた人…、彼らは今どんな思いでいるのだろう。例のジャ・ジャンクー監督を招いてのイベントも、このうねりの彼方に消えてしまった。 もし、この「中国水墨画の美」講演会も巻き込まれていたら、一年前からのアポ取りや日程調整、会場の確保、懇親会の料理の打ち合わせなどが、全部水の泡となる。 40年前の明日は、「日中共同声明」調印日だ。そこへと辿り着けたのは、「求大同、存小異」の精神があったからである。友好の礎を作り上げた、周恩来総理や田中角栄首相をはじめとする先人たちは、40年間積み重ねた日中交流の行方がこのような始末だとは、想像もしなかっただろう… 現状を見過ごせず、とうとう思いがけない人物が立ち上がった―作家の村上春樹氏。今朝の「朝日新聞」のトップで、氏の寄稿が報じられた。 「魂の行き来する道筋を塞いでしまってはならない」という言葉に、心が震えた。 ぶ厚い本を読むのが苦手な私だが、村上氏の長編エッセイ集『遠い太鼓』だけは二度も熟読した。地中海の国での滞在記が、洒落た感覚とユーモラスなタッチで綴られている。が、それは喫茶店でしか読む気にならない。ロマンチストとばかり思っていた村上氏だが、今回取られた行動から、孔子の言葉が思い浮かんだ。 「有徳者必有言、仁者必有勇」 (四) 両岸の喧騒も知らず、秋の虫が鳴く中、後期の開講日を迎えた。 あっ髪を切った、あっメガネをかけた… と点呼しながら、再会の懐かしさに浸っている。 「中国の言語と文化」のゼミでは、なんと7つもの新顔があった。よくもこんなご時世に、途中から履修してくれるものだ! 授業の最後に、「興味があったら、帰ってから読んでみてください」と、村上さんの例の寄稿文を配り始めた。 「先生、一つ聞いていいですか?」とある女子学生。 「どうぞ」 「先生は学生時代、釣魚島について勉強したことがありますか?」 「ありません」 そして次のことを述べた。 歴史の授業を受けた78年は、日中平和友好条約が結ばれた年であり、それからの十年間は、日中ハネムーンの時代とも言われていた。釣魚島は話題になっていなかった。 また、高校の歴史の授業では、日本で近代に入ると駆け足になるが、中国では古代から同じペースで教える。日中戦争について勉強する時、正直な気持ち、聞きたくはなかった。辛すぎるからだ。先生も学生のそんな気持ちを察していたようで、 「千年以上にもわたる中日交流の歴史の中で、たしかに不幸な時代がありましたが、友好交流の歴史の方が遥かに長いことを、忘れないでください」とおっしゃった。その言葉は、私の救いとなった。 真剣なまなざしで私を見ている学生たちに、さらに次のエピソードを話した。 私の日本の大学院の指導教官は、日中戦争下の学生時代、第二外国語である中国語を勉強していた。教師は華僑の方で、品の良い男性だった。ところが、ついに指導教官のところにも赤紙が来た。突撃の訓練中、これから先生の祖国へ人を殺しに行くと思うと、心にわだかまりがあった。幸い、戦場へ赴く直前に戦争は終わった。だが、1学年先輩はたくさん帰らぬ人となったそうだ。 「…だから、今こうして私は続けて中国語を教え、皆さんも学ぶことができています。日本と中国、なんと平和な時代が来ていることでしょう。ただただ、感謝です」 話の途中で、授業の終わりを告げるチャイムが鳴った。しかし、学生たちはみじろぎ一つしなかった。 ______________________________________________ ─会報部会からのお知らせ─ ・会報の送付に際して、会員の方々が開催される展覧会・演奏会などのチラシを同封することが可能です(同封作業の手数料として、1回1000円をお願いいたします)。ただし、会報の発行時期が限られていますので、同封ご希望の場合、詳細についてはあらかじめお問い合わせをお願いします。次号の会報は、4月発行の予定です。 ・会員の関係する催し等の告知についても、会報への掲載が可能です(今後は、学会ホームページの活用も予定しています)。こちらについても、詳細は下記までお問い合わせ下さい。 (会報部会:082-225-8064、baba@eum.ac.jp)