

広島芸術学会会報 第135号
● 巻頭言
黄霊芝さんの日本語創作について
下岡友加(県立広島大学人間文化学部准教授
2007年、資料調査のため台湾に滞在していた私は、台北在住の黄霊芝(1928-)さんに会うことができた。黄さんは創立当初(1970)より台北俳句会の主宰をつとめる俳人・作家・彫刻家である。台湾独自の季語をまとめた『台湾俳句歳時記』(言叢社、2003)により、第三回正岡子規国際俳句賞を受賞している。黄さんの自宅でひとしきり歓談した後、帰り際、十数冊に及ぶ『黄霊芝作品集』(自費出版)を頂いた。それらの殆どは日本語で書かれたものであった。周知の通り、戦後台湾の公用語は中国語となり、日本語の創作は売り物にはならない。しかし、日本統治下の台湾で17歳まで日本語教育を受けた黄さんが最も得意とする言語は日本語であった。黄さんは母語である台湾語のほか、後年になって中国語、スペイン語、フランス語を身につけたが、「日本語ほど繊細な言葉はない」と創作言語としてあえて日本語を選択したのである。
『黄霊芝作品集』に目を通した私は、掲載された小説、童話、短歌、論説等の完成度の高さに舌を巻いた。黄さんの創作は日本の近代を代表する作品に比べても全く見劣りしないのである。その後、私は黄さんの小説を学生たちと一緒に読む授業を勤務校で開始し、今年で7年目に入る。2012年には黄さんの許可を得て広島の溪水社から『戦後台湾の日本語文学 黄霊芝小説選』を刊行した(続編も2015年に刊行)。現在、授業には台湾・世新大学からの交換留学生・潘さんも参加している。脚本家を目指している潘さんは、つい最近、私に嬉しい計画を打ち明けてくれた。半年後に台湾の母校に戻ったら、黄さんの小説を原作に日本語演劇を上演したいというのである。
これまで黄さんの日本語文学は、「日本文学」と「台湾文学」の狭間にあって、その存在すら十分に認知されることなく等閑視されてきた。そんな中、潘さんの提案は一つの明るい希望である。大袈裟な言い方かもしれないが、黄さんの文学が確かに台湾の後継に命をつないだのだから。
戦後台湾における黄さんの日本語文学とは、その存在自体が日本の植民地支配の事実を決して忘れさせない記録、〈記憶の装置〉である。また、戦後の体制(国民党政府)からすれば、日本語はかつての敵戦国の言葉=〈異物〉に他ならない。黄さんの日本語創作とは実は極めて反権力的な命知らずの方法でもあった。しかし、黄さんはそうした政治色をあからさまに掲げることを嫌い、むしろ世界共通である不完全で愚かな生き物としての人間の悲喜劇を、饒舌な語り口とユーモアをもって提示することに専心した。
ドイツ語と日本語で創作する作家・多和田葉子は「言葉遊びは閑人の時間潰しだと思っている人がいるようだが、言葉遊びこそ、追い詰められた者、迫害された者が積極的に掴む表現の可能性なのだ」(『エクソフォニー―母語の外へ出る旅』岩波書店、2003)と述べている。まさしく黄さんの営為にもあてはまる言葉であり、彼の文学は日本語を介して芸術の根源的な力を改めて我々に教えてくれるのである。
● 第112回例会報告
◇ ヒロシマ・アート・ドキュメント(Hiroshima Art Document)
―アートを巡るフリー・トークの会―
報告:大島徹也(広島大学大学院総合科学研究科准教授)
戦後70周年にして Hiroshima Art Document 20周年にあたる2015年、第112回例会ではHiroshima Art Document 2015 の展覧会会場(旧日本銀行広島支店)に出展作家と当学会会員らが集まって、アートの現状について自由に話し合う座談会が行われた。出展作家からは、ジュディット・カエン氏(フランス)、江口方康氏(日本)、セシール・アートマン氏(フランス)、ハンス・ヴァン・ハウエリンゲン氏(オランダ)が参加した。座談会では、それに先立つ同日の上映会で発表されたカエン氏と江口氏の共同制作映画『幻影の未来』や、その他の作家の展示作品のそれぞれのコンセプトに着目しながら、第二次世界大戦、原爆、東日本大震災、原発事故などと現代アートとの関係が多角的に議論された。なかでも、戦争という文脈から広島の街を現代アートの主題に用いることの是非、広島の人間でない者が広島の地で原爆という問題について表立って何か意見を表明することへのためらい、震災の被害を直接に受けなかった者が震災をテーマにいかにして芸術作品を制作していくか、といった問題について、参加者各人のさまざまな立場からの忌憚のない意見が、日本語と英語とフランス語を用いて交わされた。
予定時間を15分ほど過ぎたところで、フリー・トークを趣旨とした本座談会では最後に何らかの全体的な結論を出したり合意を形成しようとするよりは、今日の議論の中で自分の心に響いてきた問題を各人が持ち帰り、今後の自身の活動に役立てていこうということで、本座談会は盛況のうちにお開きとなった。
● インフォメーション
【会員の出版】
谷藤史彦『祭りばやしのなかで 評伝 高橋 秀』(水声社) 本体3,800円(ISBN 978-4-8010-0132-9)
このたび会員・委員の谷藤史彦さんが『祭りばやしのなかで 評伝 高橋 秀』を出版されました。ふくやま美術館学芸課長の谷藤さんが、福山出身で「エロスの画家」として知られる高橋秀氏のこれまでの人生を、深く総合的にとらえた評伝です。本学会の大会で講演をされたことがある高橋氏の少年時代の話や在イタリア時代のエピソード、近年の活動などが余すところなく語られています。
能登原由美『「ヒロシマ」が鳴り響くとき』(春秋社) 本体2,200円(ISBN 978-4-393-93592-7)
このたび会員の能登原由美さんが『「ヒロシマ」が鳴り響くとき』を出版されました。現在、「ヒロシマと音楽」委員会委員長を務めておられる能登原さんが、1995年から携わってきた「ヒロシマ」に関わる音楽作品のデータベース化事業をもとに、そこから見えてきたさまざまな問題意識を、戦後70年の、音楽から見た「ヒロシマ」像とその歴史的変容としてまとめたものです。
※ 会員の皆さまの活動(出版、作品展、コンサート、受賞、等々)について、随時、会報にて告知いたします。掲載事項のある方は、どうぞご遠慮なく、事務局までご一報ください。
─事務局から─
◆ 平成27年7月?11月入会者(敬称略、承認順)
松本侑子(まつもと ゆうこ)(19世紀フランス美術)、渡辺千尋(わたなべ ちひろ)(ピエール・ボナール、19世紀から20世紀にかけての欧米のアートマー ケット)、李 京彦(イ ギョンオン)(写真、視覚文化論)、森下麻衣子(もりした まいこ)(近代日本美術)、五味あずさ(ごみ あずさ)(浮世絵研究)、于 君(ユ ジュン)(日本中世軍記物に表された武士像)
─会報部会から─
・チラシ同封について
会報の送付に際して、会員の方々が開催される展覧会・演奏会などのチラシを同封することが可能です(同封作業の手数料として、1回1000円をお願い いたします)。ただし、会報の発行時期が限られるため、同封ご希望の場合は、あらかじめ下記までお問い合わせください。次号の会報は、2月中~下旬 の発行を予定しています。
・催しや活動の告知について
会員に関係する催しや活動を、会報に告知・掲載することが可能です。こちらについても、ご遠慮なく、下記までご連絡、お問い合わせください。
(馬場有里子090-8602-6888、baba@eum.ac.jp)
<広島県立大学サテライトキャンパスひろしま 地図>
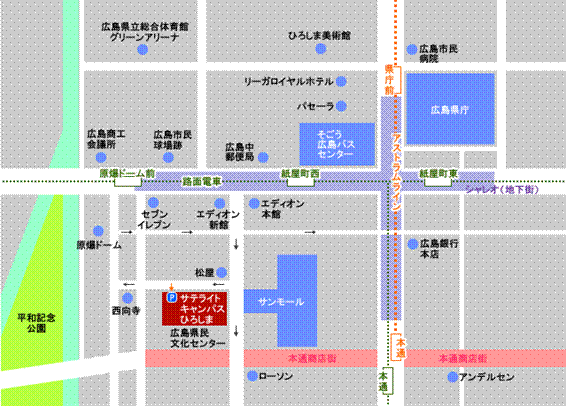
― 次回第113回例会のご案内 ―
下記のとおり第113回例会を開催いたします。お誘いあわせの上、多数ご参加ください。
なお、例会終了後に懇親会(忘年会)を予定しています。
例会日時:2015年12月26日(土曜)、14:00~17:00
場所:広島県立大学サテライトキャンパスひろしま 604中講義室
730-0051 広島市中区大手町1丁目5―3(広島県民文化センター内) ※前ページの地図参照
● 研究発表① 『太平記』に描き出された武士像:「忠」と「孝」を中心に
于 君(広島大学大学院教育学研究科 博士課程後期)
● 研究発表② 西山翠嶂に関する一考察 ―竹内栖鳳と浅井忠のはざまで―
森下麻衣子(海の見える杜美術館)
<発表要旨>
①『太平記』に描き出された武士像:「忠」と「孝」を中心に
『太平記』中の武士の中で、最大の「忠臣」として描かれ人々に馴染みがあるのは、楠木正成である。またその子の正行も「忠孝」を代表する存在として、長い間人々の脳裏に深く根付いてきた。こうした正成・正行像の定着の理由としては、『太平記』中の正成・正行関連の記述に起因するほか、戦前までの『太平記』受容史が深く関わってきたことも考えられる。従来、「忠臣」という概念で『太平記』中の武士(公卿も含め)について言及する際、その多くは南朝方の武士をその対象としてきた。しかしながら、『太平記』中には、南朝を軸とした「君臣関係」以外に、北朝側の「君臣関係」、あるいは武士間の「君臣関係」における「忠」の表現も見出すことが出来る。
本発表では、楠木正成・正行父子に代表される『太平記』中の武士像を再考するとともに、南朝側の武士に限らず、また限定的な「君臣関係」の枠組にもとらわれず、さまざまな武士における、「忠」、「孝」に関わる具体的記述に着目して、『太平記』中に描き出された多様な武士の姿について考察する。その際には、『太平記』における記述の特徴を確認し、対照させるため、先行する軍記物語『平家物語』に描き出された「忠臣孝子」像についても触れておきたい。こうした考察を通して、「忠」と「孝」という二つのことばによって描き出された『太平記』の武士像の一端を明らかにしたい。
②西山翠嶂に関する一考察 ―竹内栖鳳と浅井忠のはざまで―
西山翠嶂(1879‐1958)は、竹内栖鳳の弟子の一人であり、戦前から戦後にいたるまでの京都画壇を牽引した画家の一人である。文展・帝展で賞を重ね、審査員となったほか、京都市立美術大学等教育機関で教鞭をとった。また、彼の主催した画塾・青甲社は、上村松篁、堂本印象、三谷十糸子、西山英雄などの戦後の日本画界を変えていく存在となる重要な画家を生んだ。これほどの影響力のあった画家でありながら、彼の画業を論じた研究はいまだに多くない。先行する研究では、翠嶂が栖鳳に師事した以外にも洋画家・浅井忠に洋画のデッサンを学んだことが人物表現に大きく影響していることが指摘されている。またこのほかにも、画題・構図を江戸時代の書物に取材して描いていることも言及されてきた。しかし、栖鳳の弟子という言説が彼に常につきまとう現実がある中で、画業における栖鳳からの影響は明らかではないといえる。
本発表では、彼の画業の中でも異色といえる日露戦争に取材した六曲一双?風《日露戦争之図》(海の見える杜美術館所蔵)等の作品および残された大下絵を取り上げ、これらがいかなる契機でもって描かれたかを考察する。そしてそれらに見られる竹内栖鳳、浅井忠の影響に加え、中国古画、および他の同時代の洋画家からの影響を具体的に指摘し、彼の画業の特質とその確立にいたるまでの経緯を明らかにする。

